強制性交致傷での無期懲役判決と、性犯罪者の再犯率・終身刑化の可能性
はじめに
2023年10月18日、大阪地裁において、強制性交致傷などの罪に問われた元病院職員・柳本智也被告(28)に対し、求刑通り無期懲役の判決が言い渡されました。本件は被害者への悪質かつ執拗な暴力行為が問題視されたほか、社会的弱者を狙った犯罪態様などが厳しく非難される要因となりました。性犯罪は被害者に深刻な肉体的・精神的被害をもたらすだけでなく、その再犯リスクも注目されがちな分野です。
無期懲役とは、いわゆる“仮釈放の可能性を残したまま生涯刑務所に収容されうる”刑罰ですが、性犯罪で無期懲役に処された受刑者が実際に出所した後、どの程度再犯しているのかについては、公式の統計が乏しく、一般的にはあまり知られていません。また、日本においては死刑と並行して「終身刑」という選択肢が存在しないため、無期懲役そのものが“事実上の終身刑”となっている側面もあります。本稿では、性犯罪で無期懲役になった場合の再犯率や、終身刑導入の可能性について探っていきたいと思います。
強制性交致傷で無期懲役に至る理由
まず、性犯罪であっても、必ずしも無期懲役に直結するわけではありません。強姦や強制性交に関する法定刑は厳しく設定されているものの、量刑は犯行態様や前科の有無、被害状況によって幅があります。無期懲役にまで至るケースというのは、殺人に匹敵するほど重大で悪質な結果を生じさせた場合や、被害者の数が多数に及ぶ連続犯罪である場合、あるいは犯行の手口が特に残虐かつ計画性が高い場合などに限られます。
今回の柳本被告のケースは、被害者が特別な保護を要する立場(患者や弱者)であったことや、その行為の悪質性から、検察は「社会に与える影響が大きく、更生可能性も低い」と主張し、無期懲役を求刑しました。そして、裁判所もこれを追認する形で量刑が確定したわけです。

性犯罪で無期懲役に服する受刑者の仮釈放
日本では、無期懲役囚が仮釈放を申請できるのは、刑に処されてから10年を経過して以降とされています。しかし、実際には20~30年、あるいはそれ以上の長期収容が一般的となっており、仮釈放が認められる事例は決して多くありません。とりわけ、今回のように「性犯罪」で無期懲役とされた受刑者は、その重大性や再犯リスクの高さが懸念されるため、仮釈放に至るハードルはさらに高くなると考えられます。
仮釈放を判断する際には、刑務所内での規律順守態度や作業実績、反省の度合い、被害者や遺族の意見、身元引受人の存在など、さまざまな要素が評価されます。性犯罪の場合、加害者が心からの反省を示し、更生プログラムを受けていても、外部での監督体制が不十分であれば社会復帰後に再び被害者を出してしまうリスクがあるとして、仮釈放の審査は慎重のうえにも慎重が求められるのです。
再犯率の実態:限りなく少ない母数と厳しい統計の壁
結論から言えば、「性犯罪で無期懲役に処され、出所後に再度重大な性犯罪を犯した」ケースの件数や統計データは、非常に限られています。無期懲役受刑者全体の仮釈放自体が少ないことに加え、さらに性犯罪特化のデータとなると公的機関が詳細に公表している例は見当たりません。
ただし、一般的に無期懲役を言い渡される受刑者の仮釈放後の再犯率は、数値上は低い傾向にあるといわれます。というのも、10年や20年以上にわたって服役し、社会から隔絶されるうえ、刑務所内での矯正プログラムを受け続けることで、一定の更生を果たしていると判断されなければ仮釈放は許可されにくいからです。また、仮釈放が許可された後も保護観察所による厳格な監視や支援が伴うため、「再犯そのもの」が起こりにくい構造になっています。
しかしながら、性犯罪は「依存傾向」や「特定の嗜好」などが強く働く場合があり、単なる反省や規律順守だけでは更生を証明しづらい面があると指摘されています。その結果、「もし仮釈放を許可した被告が再犯すれば、社会的な非難は避けられない」というリスクを鑑み、性犯罪での無期懲役囚に対する仮釈放がいっそう厳しくなる実態があると言えるでしょう。
小学生女児計10人に対しカッターナイフを示しながら「家族を殺すぞ」などと脅して性的暴行を加えた柳本智也、これはもう無期懲役どころか死刑レベルの話だよな。
— カポ峯 (@capone777x) February 4, 2025
まだ幼い女児達が受けた精神的苦痛は筆舌に尽くし難いものだっただろう。
もし自分に娘がいてこんな事されたら絶対に許せねえだろうな。 pic.twitter.com/skphvJ1mrY
日本における「終身刑化」の可能性
日本には欧米のような「仮釈放なしの終身刑」は存在せず、現行制度の無期懲役が一種の“終身刑的役割”を担っています。死刑を除けば最重刑となる無期懲役に関して、「実質的に終身刑ではないか」という見方もありますが、法律上はあくまで仮釈放の可能性を排除していません。
近年、一部では「死刑制度を廃止する代わりに、仮釈放のない終身刑を導入すべき」という議論や、「重大な性犯罪者には死刑よりも終身刑の方が適切ではないか」という声も聞こえます。しかしながら、日本社会ではまだ死刑支持の世論が根強く、同時に終身刑を導入すれば“死刑は軽くなる”といった錯覚を招く恐れもあり、政治レベルでの大幅な制度改正には至っていないのが現状です。
一方で、無期懲役の長期化が進み、仮釈放を認められないまま高齢化し、病死や老衰で刑務所内で亡くなる受刑者が増えているという実態もあり、事実上の終身刑が運用されているとの指摘もあります。性犯罪のなかでもとりわけ重大な事案においては、仮釈放までの道のりがなおさら厳しくなると考えられるため、ほぼ「生涯収容」に近い扱いが今後も続くことが予想されます。

おわりに:再犯防止と被害者救済の両立を求めて
今回、柳本智也被告に対し、求刑通り無期懲役が言い渡されたことは、社会に対する厳格な処罰姿勢を示す象徴的な判決とも言えます。一方で、性犯罪全般に対しては再犯防止プログラムの強化や被害者支援の拡充など、刑罰以外の観点からアプローチする試みが重要であるのも事実です。
日本の刑事政策は、被害者感情の尊重と更生の可能性の両立を模索してきました。無期懲役という長期の自由刑は、その両面を担保する一つの手段ですが、さらに踏み込んで「終身刑」を導入するべきかどうかは、依然として大きな議論の余地があります。何より、被害者が再び被害を受けることのないよう厳格に対処しつつ、仮釈放の審査では真摯な反省と再犯リスクの評価をより丁寧に行う必要があるでしょう。
性犯罪の再犯率は一様ではなく、個々の犯罪者の背景や治療、支援環境によっても左右されます。とはいえ、無期懲役となるほどの重大事案では、社会が受ける衝撃と被害者救済の重みを踏まえれば、長期収容やほぼ終身的な拘禁となる可能性が極めて高いのが現実です。この現実を踏まえつつ、今後も終身刑化をめぐる議論や再犯防止の取り組みの充実が求められると言えるでしょう。
PR:
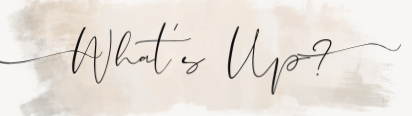



コメント